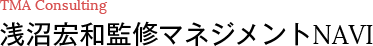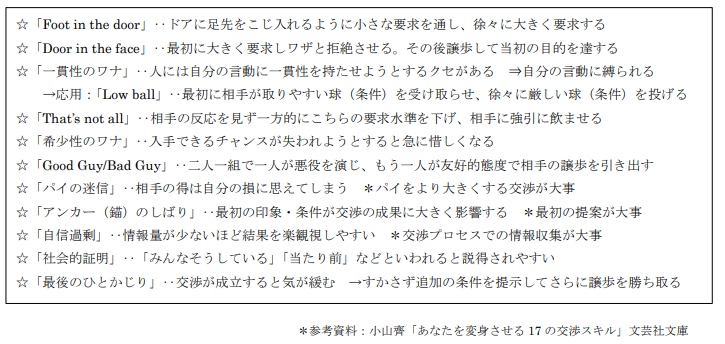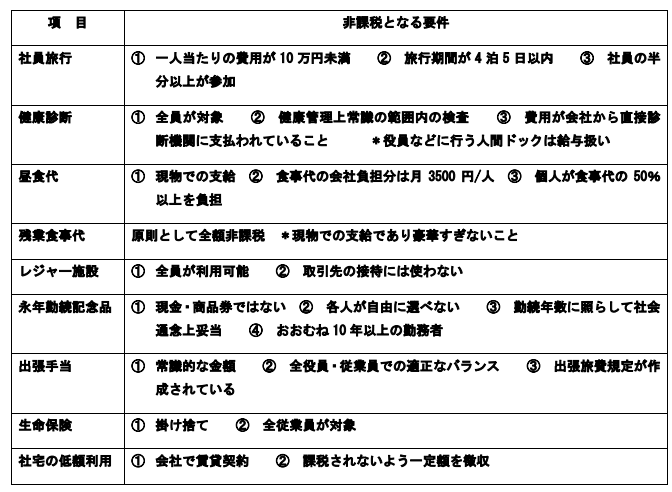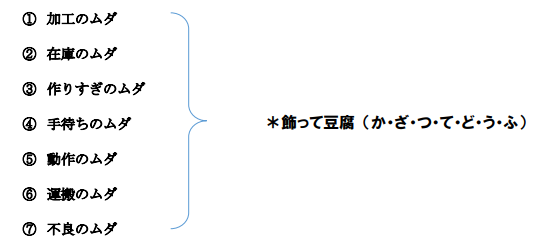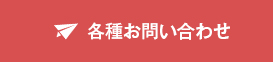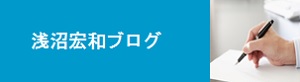今月はドラッカーの名言から、経営に関するものをご紹介します。
1. 成果を生み出すために、既存の知識をいかに有効に適用するかを知るための知識が、マネジメントである。
2. 企業の目的が顧客の創造であることから、企業には二つの基本的な機能が存在する。すなわち、マーケティングとイノベーションである。この二つの機能こそ起業家的機能である。
3. 強みは企業によって異なる。それはいわば個性である。しかし、あらゆる企業、あらゆる組織が持つべき共通の強みがある。イノベーションの能力である。
4. イノベーションは市場に焦点を合わせなければならない。製品に焦点を合わせたイノベーションは新奇な技術を生むかもしれないが、成果は失望すべきものとなる。
5. すでに発生していながら、その経済的な衝撃がまだ現れていない変化がイノベーションの機会となる。
6. マーケティングは顧客の現実・欲求・価値からスタートする。「われわれの製品サービスにできることはこれである」ではなく、「顧客が価値ありとし、必要とし、求めている満足はこれである」という。
7. 主力製品に際立った個性がなく、市場でリーダーシップを握っているという確証がないのなら、売上や利益が順調なうちに手を打たなければならない。
8. 顧客と市場を知っているのはただ一人、顧客本人である。したがって、顧客に聞き、顧客を見て、顧客の行動を理解して初めて、顧客とはだれであり、何を行い、どうやって買い、何を期待し、何に価値を見出しているかを知ることができる。
9. 企業が自ら生み出していると考えるものが重要なのではない。特に企業の将来や成功にとって重要なのではない。顧客が買っていると考えているもの、価値と考えるものが重要である。それらのものが、事業が何であり、何を生み出すかを規定し、事業が成功するか否かを決定する。
10. 既成の事実が、事業にとっていかなる意味を持つか、いかなる機会を作り出すか、いかなる脅威をもたらすか、いかなる変化を要求するか、いかなる変化を可能にし、いかなる変化を有利とするかを問わなければならない。
11. イノベーションは理論的な分析であると同時に知覚的認識である。外に出て、見て、問い、聴かなければならない。